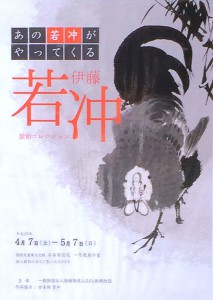月例会見学ご希望の方々へ
見学希望の方は、5月18日(木)まで「添付申し込み書」に必要事項を記入の上、事務局へ月例会担当の日野宛にFAX(03-3759-7103)でお申し込み下さい。見学詳細こちらからご連絡いたしますので、必ずご連絡先を明記して下さい。もし明記がない場合は受付できません。なお、当日見学代として1,000円ご用意下さい。また、見学者が多い場合はお断りすることもありますので、お早めにお申し込み下さい。
なお、今月は総会がありますので、宍倉ゼミの見学だけとなりますのでご了承下さい。
FAX 申し込み書<Wordファイルです>
entry@washiken.sakura.ne.jp
WEB 申し込み書<Wordファイルです>
5月例会
日 時:5月20 日(土)13:30~14:40
会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室
13:00 ~ 13:30 フリートーク
13:30~14:40 宍倉ゼミ( 特別講義は「ゼミ」と呼称を変更しました )
「戦国時代の紙と武将」宍倉佐敏 会員(下記参照)
以降 定期総会
第9回 宍倉ゼミ PC・プロジェクター・DMS使用
題名 和紙の歴史 近世の和紙 -1
『製紙が地方の主な産業になり、紙の種類も生産量も増大した』
宍倉佐敏 会員
江戸時代は町人も紙の消費者になり、紙の種類も多くなり、生産量も拡大して製紙が我が国を代表する産業の一つに数えられ、紙は日常生活の必需品となった背景や、需要の高い庶民の紙「半紙」「チリ紙」などの製法と特徴や紙漉き農民達の厳しい生活などの様子を探る。
近世に作られた数多い紙の中で、後に江戸の三大和紙と呼ばれた「檀紙」「杉原紙」「奉書紙」の調査結果と江戸時代に大名たちの間で急激に話題となった「白石紙布」の製法と特徴を纏めてみる。
「檀紙」「杉原紙」「奉書紙」をDMSで分析予定。

2017年5月9日 |
トピック:例会
◆会員情報
【景和コレクション 伊藤若冲展】
景山由美子 会員関連
日 時:2017年4月7日(金)~5月7日(日)9:00~16:00
会 場:石谷家住宅(いしたにけじゅうたく)
[国指定重要文化財・国登録記念物(庭園)]一号蔵
〒689-1402鳥取県八頭郡智頭町智頭396番 電話0858-75-3500
江戸時代の天才画家:伊藤若冲の展覧会が、鳥取・智頭にある国指定重要文化財「石谷家住宅」にて開催中。昨秋の「生誕300年記念 若冲の京都 KYOTOの若冲展」(京都市美術館)に出品された、古美術景和が所有する水墨画7点を展示。鳥取初の若冲展覧会となる。
石谷家住宅は、江戸時代に鳥取藩最大の宿場町として栄えた鳥取県八頭郡智頭町にある、敷地面積3000坪、部屋数40、土蔵7を数える近代和風建築。石谷家は明治以降、林業で財を成した地主で、主屋など8棟および敷地が国の重要文化財に指定され、玄関棟など5棟、関係文書および棟札が重要文化財の附指定となっている。庭園は池泉庭園、枯山水庭園、芝庭などで構成され、国の登録記念物、鳥取県の名勝に指定。
今回、展覧会が開催される「一号蔵」は、もと米倉を利用した展示施設で、美術・工芸関係の特別展が開催され、こちらも重要文化財に指定されている。
出品作品
「竹に雄鶏図」・「牛図」・「鷹図」・「狗子図」・「鯉図」・「蝶に狗子図」・「双鶴図」
関連HP http://www.ifs.or.jp/index.html
1、 ポスター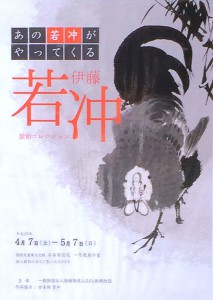
2、 会場入口
3、 展示風景
4~7、会場風家


2017年4月24日 |
トピック:会員情報
◆産地交流
今年度は色々な産地と交流を考えておりますが、昨年から始まった小川のトロロアオイ、そして、来年に向けて越前の紙の神様などからお知らせしていきたいと思います。
「大切な国産和紙原料 ―トロロアオイの作付け―」
昨年10月に「緊急報告及び急募「トロロアオイ希望者求む」というお知らせをしましたら、全国の紙すき産地・工房の方々から温かいご協力をいただき、事情によって生産過剰分になってしまった分は無駄にすることなくすみました。生産者の代表である黒沢岩吉さんが、3月の和紙研例会にいらっしゃって、報告と謝意を表されたことはFBでもお知らせしておりました。
昨年はこういう状況だったために、生産者の方々は今年度の作付けをどうしたらいいか、不安定な状況にあるようです。そこで、受注生産体制にすれば、紙すき産地・工房の方々の原料確保も可能になり、黒沢さんたちも生産が安定することとなり、現在必要分を昨年ご協力いただいた方々にお尋ねしているようです。
それらの情報をもとに、今月末頃に作付け会議を行なうそうですので、もし、必要な方々がありましたら、4月20日まで下記アドレスの販売担当者にお問い合わせいただくか、和紙研産地交流担当の日野までお問い合わせ下さい。
販売担当情報:http://washiken.sakura.ne.jp/date/2016/10/
和紙文化研究会(日野まで) entry@washiken.sakura.ne.jp
和紙原料の作付けから収穫まで、このHPで状況をお知らせして行こうと考えております。和紙作りに大切な国産和紙原料ですから、みなさんで見守って行きましょう。

「紙の神様 ー壱千三百年の大祭・御神忌」
越前和紙の源といえる有名な紙祖神 岡太神社・大瀧神社では、毎年春と秋に例祭が行なわれていますが、来年の平成三十年は「千三百年の大祭」を迎えます。この1300年という時間の経過は、和紙が日本文化として長き歴史を有することと、生活の中に根付いてきたことがわかり、和紙が日本にとってどれだけ重要なものであるか意味するもので、越前五箇地区のみならず、国内の和紙関係者にとっても大きなできごとと考えられます。
来年の春5月の「一壱千三百年の大祭・御神忌」には和紙関係者の多くの参加が足を運ばれると想像しますが、この一年、このHPでは和紙の歴史をこの1300年の祭事からかいま見たいと考えております。
平成三十年 一壱千三百年の大祭・御神忌予定
5月2日 お下り
3日 法華八講
4日 式典
5日 お神輿渡り お上り
今年の春の例大祭情報
日 時:2017年5月4日 9:00
場 所:岡太神社・大瀧神社
〒915-0234 福井県越前市大滝町23-10 電話0778-42-1151
両神社の春祭りは5月3~5日の3日間行なわれておりますので、詳しくは下記HPをご参照下さい。
http://www.washi.jp/history/index.html
http://www.washi.jp/history/maturi1.html
http://www.washi.jp/history/maturi4.html
過去の「春の例大祭風景」






2017年4月11日 |
トピック:産地交流
◆和紙情報
森のはこ舟アートプロジェクト
出ヶ原紙復活再生・「森を漉く 滝沢徹也」の成果展示会
期 間:2017年3月18日(土)~5月7日(日)9:00~17:00 休館日:毎週月・火曜日(祝祭日を除く、臨時休館日あり)
会 場:西会津国際芸術村
福島県耶麻郡西会津町新郷大字笹川上ノ原道上5752
Tel/Fax 0241-47-3200
入場料:無料
美術家・滝沢徹也氏が2年に渡り取り組んだ出ヶ原紙復活再生プロジェクト。その出ヶ原紙の歴史的背景を素地として取り組んだ 森のはこ舟アートプロジェクト西会津エリアプログラム「森を漉く」の成果展示会。
主 催:福島県・森のはこ舟アートプロジェクト実行委員会事務局:NPOふくしまアートネットワーク
共 催:東京都/アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)?協 賛:日本たばこ産業株式会社
協 力:心の復興推進コンソーシアム
助 成:文化庁
問合せ:西会津国際芸術村 TEL:0241-47-3200(楢崎)
http://www.morinohakobune.jp/
http://www.morinohakobune.jp/news/20170306.html
1、 ワークショップ 森を漉くー成果品1
2、 ワークショップ 森を漉くー成果品2
3、 出ヶ原紙用具1
4、 出ヶ原紙用具2
2017年4月11日 |
トピック:和紙情報
◆和紙情報
シンポジウム「京都学・歴彩館グランドオープン記念事業『京都の文化ー京都学・歴彩館からの発信』」
期 間:2017年4月27日(木)13時~16時
会 場:京都府立 京都学・歴彩館 大ホール
〒606-0823京都市左京区下鴨半木町1-29 電話:075-723-4831
開会挨拶: 山田啓二 京都府知事
基調講演:「歴史の裏話~史料の保存・公開とその意義~」
公益財団法人永青文庫理事長 細川護熙氏
パネルディスカッション:
国立国会図書館関西館館長 片山 信子氏
平等院住職 神居 文彰 氏
元ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院日本研究センター長
シュテファン・カイザー 氏
コーディネーター:金田章裕(京都学・歴彩館館長)
定 員:300名(参加費無料 事前申込制)
申込方法:4月3日(月)から4月17日(月)までに電話・はがき・FAX・メールにて。<当日必着・応募多数の場合は抽選>
受 付:府民生活部府民総合案内・相談センター
電話 075-411-5000 Fax: 075-411-5001 E-mail: 411-5000@pref.kyoto.lg.jp
※参加証ハガキを返送します。なお、当日は参加証ハガキを持参の方のみシンポジウムの入場ができます。ご注意ください。
主催: 府立京都学・歴彩館、府立大学、府立医科大学
関連HP
http://www.pref.kyoto.jp/rekisaikan/event/grandopensympo.html
2017年4月11日 |
トピック:和紙情報
« 古い記事
新しい記事 »