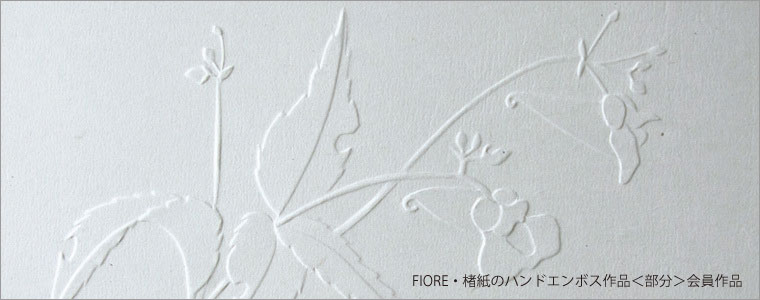例会案内
Zoomで配信 和紙研オンライン月例会・見学のご案内
◆ 7月例会 ハイブリット型 (オンライン+会場)
日 時:2024年7月20日(土) 13:30~16:10
会 場:小津和紙6FとZoomによるオンライン配信
タイムスケジュール
13:30~15:00 「幻の博物館の紙-日本実業史博物館旧蔵コレクション-」
青木睦会員
*13:00からZoomの会議室への接続ができますが。
※ プログラムや機材の関係で、時間が変わる可能性があります。予めご了承ください。
会員発表2-2
題 名 「幻の博物館の紙-日本実業史博物館旧蔵コレクション-」
青木 睦 会員
日本実業史博物館は、渋沢栄一の没後、その遺徳顕彰記念事業として企画された。資料収集は、栄一の孫である渋沢敬三を中心に行われたが、第二次世界大戦により博物館設立計画は頓挫し、収集資料は当館(旧文部省史料館→国文学研究資料館)に寄贈された。国文学研究資料館収蔵の「日本実業史博物館準備室旧蔵資料」の概要について紹介し、本報告では、『幻の博物館の「紙」』展示について詳しく紹介したい。
「紙」展示の目的は、渋沢栄一が関わったさまざまな産業部門のなかでの紙・製紙産業を実業史に関する博物館として、具体的にどのように展示しようとしたのか、遺されたコレクションから検証するところにあった。さらに、かつて生活を彩った紙製品の数々を紹介し、現在失われつつある紙文化の世界を再現、また楽しく見て触れる空間を演出した。
ここでは、「日本実業史博物館」がなぜ幻の博物館なのか、について記しておきたい。渋沢栄一が1931(昭和6)年11 月11 日に死去した後、遺言によって渋沢記念財団竜門社が渋沢栄一邸の寄贈を受けた(現在の飛鳥山公園内)。約8470 坪ほどの敷地及び建物である。1937(昭和12)年5 月、(財)竜門社は、旧渋沢栄一邸の利用に関する委員会を設置し、渋沢子爵家を栄一より継承した嫡孫の渋沢敬三ら9 名に委員を委嘱する(当時、敬三は(財)竜門社の評議員)。そして、この委員会は答申を提出し、同年7 月15 日に財団の理事会・評議員
会において、「渋沢青淵翁記念実業博物館」の建設が決議される。この決議された計画案は、渋沢敬三の「一つの提案」をベースにしたものであった。
渋沢敬三による「一つの提案」で示された「近世経済史博物館」の設立が構想された。その計画は(財)竜門社の事業として動き出し、1939(昭和14)年5 月13 日、渋沢栄一生誕百年記念祭に際し、「渋沢青淵翁記念実業博物館」建設地鎮祭を挙行する。この建設は、国家総動員法に基づく戦時経済統制の強まりによる建築資材の入手困難等により、竣工には至らなかった。その後も「日本実業史博物館」の名称でもって、その設立に向け、資料の収集および展示・収蔵のための施設の設置場所の模索が続けられが、まさに「幻の博物館」となった。
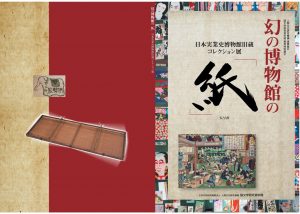


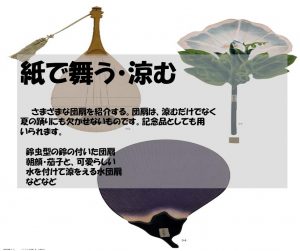
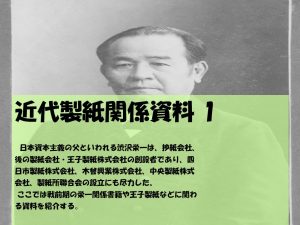
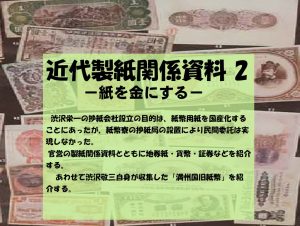
■プロフィール
青木 睦〈AOKI Mutsumi〉
1981 年~2023 年3 月 国文学研究資料館(国立史料館:国文学研究資料館史料館)に勤務。現在、学習院大学大学院でアーカイブズ管理研究Ⅲ(記録アーカイブズ保存と修復)、法政大学で文書館管理研究を担当。元全国歴史資料保存利用機関連絡協議会理事。
文化財保存修復学会業績賞(2011 年)、MLA(Museum・library・archives)、企業など、民間所在アーカイブズを含む、紙資料を主としたアーカイブズの保存修復に関する調査研究を専門としてきた。アーカイブズ保存のための物理的コントロールシステムの確立を目指す。
著書
『被災資料救助から考える資料保存 東日本大震災後の釜石市での文書レスキューを中心に』(けやき出版、2013 年)
『紙と本の保存科学』(共著、岩田書院、2009 年)
“Preservation and Conservation of Japanese Archival Documents in theVatican Library”(共編著、バチカン出版局、2019 年)など。
増田副会長からの「竹紙提供」
長らく増田副会長から皆さんに分けて下さいとして預かっていた竹紙
が1反あります。会場の制限が解錠されまし
たので、6月と7月の例会会場に来ていただければ2 枚ずつお分けし
ます。色や繊維画像(DMS200x)などはHP で紹介します。
名称:唐紙
入手:数十年前
寸法:106×54 ㎝
紙厚:0,08 ㎜
繊維:竹
なお、なくなり次第終了します。
予告:
8月例会は休会です。
9月例会は2024 年9月21 日(土)です。9月の内容は以下となります。
田中あずさ氏(ワシントン大学図書館)「AI を使用した繊維分析(仮)」
西田勝氏(西田和紙工房)「石州和紙について(仮)」
和紙研オンライン月例会の見学について
7月の見学は、下記2つの方法のいずれかで、専用〈申し込みフォーム〉からWeb申込みができます。(お手数をかけますが、これまでの方法では申込みができません)参加料金500円は同じですが、事前入金締切りは7月15日となりますのでご注意ください。
申込方法:
1、〈申し込みフォーム〉のURLを下記します。
https://sgfm.jp/f/3e9c22895411e1e136bb78bf3ab1b385
2、QRコードから読み込めます。画像を添付します。

申込期間:2024年7月15日(月)まで
参加人数:40名まで(申込み順です)
見学詳細:配信URLなどは和紙研からご連絡いたします。もし、必要事項の
明記がない場合は、受付・配信はできません。
見学回数:5回まで(以後は会員登録が必要です)
見学料金:例会1回あたり500円
料金支払:事前振込制 6月10日締切り
振込口座:郵便振替00140-0-568810 和紙文化研究会
第244回 和紙文化研究会 9月例会のお知らせ
◆9月例会
7月の例会案内でお伝えしましたように、久米前代表の講義終了に伴い、原典購読の時間など時間配分を含め例会全体の構成について検討中ですので構成が決定するまでは例会が変則的になるかと思いますのでご了承下さい。
日 時:9月17日(土)
会 場:小津和紙本社ビル 6階会議室
13時30分〜14:45 会員発表 森木佳世子会員
「極北、氷雪の世界に息づく日本の版画技術と和紙」
本年1月21日(金)~3月15日(火)までカナダ文明博物館の企画展として、カナダ大使館高円宮記念ギャラリーで「旅する版画:イヌイットの版画のはじまりと日本」が開催されました。日本国内ではこれまでイヌイットの版画展が大阪や北海道などでは企画されましたが、大々的に東京で催されるのはじめてで、様々なメディアで紹介されたことから、非常に多くの入場者を迎えました。そのほとんどは、イヌイットの版画や芸術作品に初めて触れる人々で、多くの人が、イヌイットの芸術表現とこの展覧会に深い感銘を受けていました。
実はこの版画と日本の関わりは深く、その関係性を「紙」という視点で森木会員に紐解いていただきます。発表は前述のカナダ大使館での展示概要の紹介、極北への和紙の流通経路、そして版画に使用されている紙の種類などを、国立民族学博物館研究部での発表を通して語っていただきます。
同展覧会で流されたビデオの上映と額装した原物4点の展示も予定していますので、ご期待下さい。
〈 ビデオは20分、プロジエクター、パソ コン使用、原物展示 〉
14:45〜15:00 休憩
15:00〜16:00 緊急報告 櫛笥節男会員
「東日本大震災で被災した過去帳の修理」
5月に宮城県沿岸部で被災した寺から、津波に流され、回収できた2冊の過去帳の修理依頼があった。当初、水害や火災によって大量に被災した史料の応急処置や修理は、豊富な経験を蓄積している機関が多くあり、そのようなところに任せた方が良いのではないかと考えた。
しかし、海水に浸かった紙資料はカビが生えないということを聞いており、一度どのような状態なのか見ておきたい思いもあり、その過去帳を実見したところ、自分が経験した修理方法で100パーセントとは行かないものの、高い確率で旧の状態に戻すことが可能であること、そして数量も少ないこともあり引き受けることにした。
培ってきた経験を基に工夫を重ね修理を行ない、依頼者に喜ばれたことは修理する者にとってうれしいことである。
そこで、この方法を紹介し、皆様からのご批判を頂きこれからの修理に生かしていきたい。
〈 プロジエクター、パソ コン使用、原物(白紙部分)観覧 〉
17:00〜17:20 原典購読についての意見交換。
17:20〜17:45 講演会について(8月20日の報告)
17:45〜 事務連絡・会場片付け 17時までに退出・散会。
◇「日常の和紙の使い方」(仮称)の試験ケース②はこの度「緊急報告」が入ったため10月になります。
※例会構成や時間配分などを含めどんな些細なことでもかまいませんので、ご意見・ご質問・お問い合せが ありましたら、〒・電話・Mail・直接など日野までお知らせ下さい。
◆名簿の訂正について
6月の例会案内と同封しました「会員名簿」第一面について大幅な訂正がありますので別紙添付いたします。
37白井麻美さん 所属に「昭和女子大学大学院生活機構研究科生活文化研究専攻」を追加
◆年会費について
6月にお知らせしました今年度の会費徴収状況は、賛助会員は25団体中7団体がまだです。個人会員は75人中26人がまだです。9月末日が締切となっておりますので、お早めにご入金下さい。
◆久米名誉会長の講話終了後の例会について
7月の例会案内でご連絡しましたが、久米先生の講話終了に伴い、現在「例会の構成と時間配分について」検討を始めております。
時間配分は以下のようでしたが、それを① このまま、②全体を再編、③部分再考かが考えられます。
A) 13:30〜14:30 原典購読
B) 14:40〜16:00 例会発表
C) 16:00〜17:00 連絡・報告など
A)の文献(原文)購読の内容と方式については、白戸会員から提案された案(別紙1)をもとに話合いました。 12人の方々に順番に発言してもらった結果は、
・白戸会員案の「ワーキングブループを立ち上げる」という意見に賛成が5名。
・内容やレベルは別にして、誰かに久米先生の講話方式のようにしてもらうというのが3名。
・新しい会員が増えてきたことも考え、過去に久米先生が講義した内容を輪番制で再読し、久米先生や他各 分野の先生方にコメントをいただく。
・原典(原文)よりも活字化されたものを土台としてほしい。
・これまで読んできたものを再度確認して考えてみる。(以下書名等のみ列記)
「放馬灘紙」(文物)「延喜式」「和漢紙文献類聚」「紙漉大鑑」「紙漉重宝記」「新選紙鑑」「諸国紙名録」「貿易備考」「パークス日本紙調査報告」「J・Jライン和紙論」「明治十年内国博」「紙譜」(文房四譜)「紙説」(朴学斎叢刊)「製紙」(天工開物)「日本・韓国・中国への製紙行脚」「雲南省少数民族手工造紙」「造紙史周辺」「銭存訓の中国紙論」「中国伝統手工紙事典」「正倉院文書」
和紙の製法(49回)
「延喜式 巻十三図書寮」「農業全書」「異邦珍事誌」「紙漉大鑑」「紙漉重宝記」「万宝鄙事記」「雲箋小譜」「楮木製作方紙漉立方の法」「江戸参府紀行」「紙漉必要」「厚生新編」「西洋緜紙抄紙法」「越前紙漉図説」「岐阜県下造紙乃説」「四国産楮紙乃説」「博覧会見聞録・巻乃十一」「米国博覧会報告書日本出品解説」「鷲子紙百帖紙」(江戸明治手漉紙製造工程図録」「書式の美ー懐紙・短冊ー」(明治十年勧業博覧会出品解説・抄録)「広益・農工全書」「類聚壱万伝授」「農業全書」「製紙論」(日本農業新聞)「和紙製造法」「島根県鹿足郡製紙伝習所文献」「ウィーン万国博覧会出品目録」「日本製紙論」「本邦製紙業管見」「紙の歴史」「造紙法の西伝」
9月の例会はこれらを参考に別な方々に意見をお尋ねします。
②か③として時間配分を変えてみる方法で2つの案提案があります。その中で水木会員案を試験的に行なってみることになりました。
◇「日常の和紙の使い方」(仮称)の試験ケース①について
水木会員の発案で試験的に始まりました「日常の和紙の使い方」ですが、日頃、仕事・私事に関わらず和紙に関連する作業や興味を20〜30分話していただくということです。素材は身近にあるわけですから研究発表とは違って準備にもあまり負担がかからないと考えられます。和紙研会員は様々な業種の方々がいるので、自分とは異なる使い方や考え方が多々あると考えられます。それを知ることによって会員それぞれが知識を増やし、また和紙をこれまでとは違った視点で捉えることができ、会員相互の新たなコミュニケーションが生まれたり、和紙普及の広がりにつながるのではないかということが水木会員の考えです。
まず、トップバッターとして7月例会で浅沼会員に発表していただきました。
浅沼さんは、アトリエスズキに所属しており、主に洋本修理に携わっております。今回は洋本修理の中での和紙の利用について、プロジェクターを使い修理段階を映像で示しながらわかりやすく説明してくれました。
洋本修理のことをわからない私などは、“洋本になぜ和紙なのか”“洋本には洋紙でないのか”という疑問が先立ちましたが、特にイタリアのフィレンツェで1966年に起きた大洪水でたくさんの書籍類も被害を受け、その際の復元にあたって和紙が重要な役割を果たし、その優秀性が証明された後は和紙は洋本修理の必須素材の一つになっているということで納得しました。
その理由は、①強さと耐久性、②柔軟性、③厚みの幅の広さ(薄いものから厚いもの)などが上がり、適材適所様々な部分に使われていました。和紙の種類は多くは楮紙で三椏紙なども使用。整本専門用語のクータ・ヒンジ・花ぎれ・背貼り・ジョイントなど聞き慣れない言葉も出ましたが、浅沼さんの細かい説明で理解ができました。
いつの頃から洋本修理に和紙が使われたのかわかりませんが、原物の素材が異なっていても、そのものの耐久性を保持するために使われている点は、書籍類だけに限らないのではないかとその広がりを感じました。また、洋本修理を知らない方々にとっては新たな発見もあったのではないかと、この試験発表から得る所は小さくなかったと思います。ただ、皆さんにわかりやすく紹介するための写真整理には時間がかかったようで課題が残りました。
洋本修理についてもっと詳しく知りたい方は、アトリエ・スズキのHPを参照して下さい。
試験ケース②③と10月と11月にも予定しております。
◇もう一つは私の案ですが、同じテーマで、ある一定期間(例:3回や半年)講義したり討議したりできないでしょうか。例えば「和紙とは何か」など和紙研で普通に使っている「和紙」という言葉は、実はそれぞれが異なった認識や見解を持っています。それについて考えを出し合い、できれば互いの考えを共有したり、和紙研の一定見解を導けたらどうかと考えます。和紙文化研究会や和紙研と「和紙」という言葉を高々と掲げてるわけですから、一度時間をかけて話合ってみたらどうでしょう。和紙に限らず色々とテーマは考えられます。