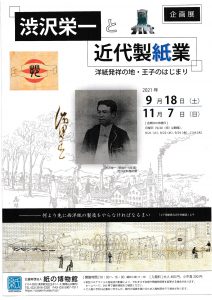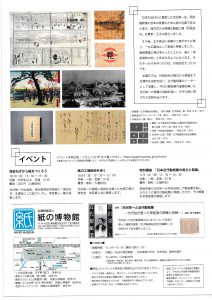◆会員情報
会員情報
TV放映
・NHK総合 歴史探偵 「写楽 大江戸ミステリー」
宍倉佐敏 会員関係
放送日:2021年9月29日(水)
再放送:毎週金曜 午前0時52分(木曜深夜)・毎週金曜 午後3時10分
浮世絵師・東洲斎写楽。衝撃デビューをプロデュースした仕掛け人とは?ギリシャで大発見!写楽の正体が明らかに?スタジオに本物も登場!最新科学で迫る大江戸ミステリー。(NHK HPより)
関連HP:
https://www.nhk.jp/p/rekishi-tantei/ts/VR22V15XWL/episode/te/6G1L5X44MK/
展覧会
「渋沢栄一と近代製紙業 洋紙発祥の地・王子のはじまり」
紙の博物館 会員関係
期間:2021年9月18日(土)~11月7日(日)10:00 ~17:00
入館は16:30 まで 休館日は月曜日(祝日の場合は開館)、祝日直後の平
日、年末年始、臨時休館日
会場:〒114-0002 東京都北区王子 1-1-3
TEL 03-3916-2320 / FAX 03-5907-7511
アクセス
電車:JR京浜東北線 王子駅南口下車 徒歩約5分
東京メトロ南北線 西ヶ原駅下車 徒歩約7分
都電:東京さくらトラム(都電荒川線)飛鳥山停留場下車 徒歩約3分
バス:都バス 飛鳥山停留所下車 徒歩約4分
北区コミュニティバス 飛鳥山公園停留所下車 徒歩約3分
関連HP https://papermuseum.jp/ja/special-exhibition/
関連書籍
「渋沢栄一と近代製紙業 ―渋沢翁が語った草創期の困難と挑戦」
販売予定価格:1000円(税込)
渋沢栄一が、近代製紙業のはじまりについて後世に語った貴重な談話「王子製紙株式会社回顧談」を、注釈付きで全文翻刻。
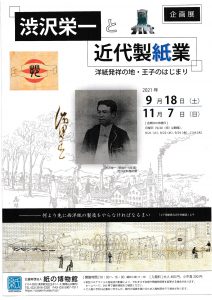
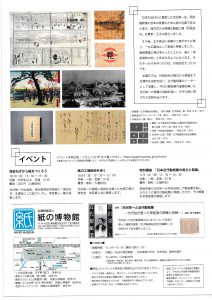
2021年9月24日 |
トピック:会員情報, 和紙情報
◆例会予告
予 告
和紙研 連続企画4回シリーズ「正倉院の筆・紙・麻を見る」
来月10月の例会より、以下の企画を開始する予定となっております。ぜひ、ご参加いただけましたら幸いです。(オンライン見学も検討中です)
【企画意図】
南都正倉院には、極めて貴重な九千件にのぼる書跡・文房具・調度品・飲食器・仏具・武器武具・楽器楽具・遊戯具・年中行事用具・香薬類など、8世紀奈良時代からの宝物が同じ場所に保存されている。千二百年以上前のものは脆弱で、“守られてきた”という言う方があたっているかもしれない。宝物は私たち日本人の文化の淵源であり、それを守ることは、誇りであって使命だったようにも思われる。
戦後、宝物の特別調査が始まって本年で43回目の報告が行われた。これらの調査分析はその時代の研究と同時に、未来に向けての貴重な示唆ともなり、非常に重要であるが、その状態から、極めて慎重に行われてきた。
和紙文化研究会には正倉院宝物特別調査に加わった会員が2人いる。「紙(第2次)調査報告」(2005~2008年)と「麻調査報告」(2013~2015年)の2度にわたり参加した当会副会長の増田勝彦氏、「筆調査報告」(2016~2019年)にあたった日野楠雄氏である。
調査員本人から話を聞くことは、報告の内容と共に、調査の臨場感などを味わうことのできる機会であり、また、貴重な話をオンラインを通して広く知っていただきたく、4回の連続企画とした。
第1回 2021年10月16日(土) 14:30~15:30
「正倉院の筆Ⅰ 絶海の弧島と紙を巻く筆とは」
―2016~2019年 正倉院宝物特別調査「筆調査報告」より―
講師 日野楠雄
第2回 2021年11月20日(土) 14:30~15:30
「正倉院の筆Ⅱ 雀頭筆の紙の質と役割」
―2016~2019年 正倉院宝物特別調査「筆調査報告」より―
講師 日野楠雄
第3回 2021年12月18日(土) 14:30~15:30
講師 増田勝彦(和紙文化研究会副会長)
第4回 2022年1月15日(土) 14:30~15:30
講師 増田勝彦(和紙文化研究会副会長)
2021年9月23日 |
トピック:例会
7月オンライン月例会 会員発表
7月オンライン月例会 会員発表 2021/7/17(土)
「和紙― 昨日・今日・明日」 田村 正 会員
田村会員は、和紙を通して自分なりの「過去・現在・未来」を思い、そして問いかけているようです。
〔昨日〕として、『和紙研究』第一号の編集後記について感じること。
〔今日〕として、小学4年生の国語の教科書に掲載された「世界にほこる和紙」増田勝彦著を見て資料を作成しました。田村会員が準備した3枚の紙を会員に郵送で配布し、オンラインでも可能な体験型の実験を行います。その内容は明かされていません。楽しみにして下さい。
〔明日〕として、現在NPO 法人向日庵理事として、昭和8 年に建てられた寿岳邸「向日庵」の保存活動していること。
【プロフィール】
田村 正(TAMUR Tadashi)1954 年 新潟県村上市生まれ
1988 年~90 年 「細川紙」伝統工芸士 江原土秋氏に師事
現在、和紙文化研究会会員・日本文化体験交流塾会員・和文化教育学会会員・NPO 法人向日庵理事・京都工芸繊維大学工芸科学部非常勤講師
関連HP(向日市文化資料館)
https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/bunka/moyoshi/1449541564567.html
2021年7月14日 |
トピック:例会
◆会員情報
会員情報
展覧会・イベント・新刊紹介
竹尾+デザインのひきだし+TOBICHI連動企画“和紙のステキさ、再発見”
「和紙の風景」展 (株)竹尾 会員関係
期間:2021年7月19日(月)~8月11日(水)11:00~18:00
休展日は土日および祝日(7月22日・7月23日・8月9日)
会場:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-18-3
アクセス:神保町駅(東京メトロ半蔵門線、都営三田線・都営新宿線)A9出口
徒歩8分
竹橋駅(東京メトロ東西線)3b KKR出口徒歩5分
古来より人から人へ受け継がれてきた紙漉きの技。
竹尾の扱う機械抄き和紙を中心に、
各地に伝わる手漉き和紙の流れを汲んだ現代の和紙の魅力をご紹介いたします。
展示内容:竹尾取り扱いの機械抄き和紙ご紹介 てまり/玉しき極薄物/やわらがみシリーズ 他 80種類以上
特別展示:株式会社竹尾創立七〇周年記念出版『手漉和紙』
特別上映:「紙の生まれる風景」
福井県 越前和紙の里/九代目 岩野市兵衛と水/紙祖神 岡太神社
主催:株式会社竹尾
協力:『デザインのひきだし』編集部、TOBICHI
関連HP https://www.takeo.co.jp/exhibition/mihoncho/detail/20210719.html
関連イベント:TOBICHI「神田かわいい和紙祭り」
会期:2021年7月22日(木・祝)~8月9日(月・祝) 11:00~19:00
会場:TOBICHI 東京都千代田区神田錦町3-18 ほぼ日神田ビル1F
関連HP https://www.1101.com/tobichi/tokyo/exhibition/detail/?p=8261
新刊紹介『デザインのひきだし43』
特集「日本の各地でつくられる魅力的な紙 和紙のステキさ、再発見」
版元:株式会社グラフィック社(Graphic-sha Publishing Co.,Ltd.)
装丁:B5判・並製・160頁
本体:2,200円
関連HP http://www.graphicsha.co.jp/detail.html?cat=4&p=44435
「和紙の風景」展は、『デザインのひきだし43』特集「和紙のステキさ、再発見」の刊行記念イベントTOBICHI「神田かわいい和紙祭り」と連動して開催いたします。
TOBICHIでは、『デザインのひきだし43』内で紹介された和紙の実物の展示や、和紙小物の販売、イベントなどが企画されています。
2021年7月12日 |
トピック:会員情報, 書籍情報
◆和紙情報
展覧会報告
膠を旅する 表現をつなぐ文化の源流
会 期:2021年5月12日(水)~6月20日(日)
会 場:武蔵野美術大学 美術館
問合せ:武蔵野美術大学 美術館・図書館
電話:042-342-6003 mail:m-l@musabi.ac.jp
この展覧会は、武蔵野美術大学共同研究「日本画の伝統素材『膠』に関する調査研究」の成果発表展として、膠づくりの歴史的・社会的背景を見つめ直す現地調査のドキュメントを中心に、壁面一杯に展示された様々な膠、原料となる幾重にも重ねられた牛一頭分の皮、他にも画材関係・様々な皮の利用風景など貴重な資料が展示され、さらには美術館所蔵の日本画等の膠を用いた作品表現もご紹介されました。
新型コロナ感染症の緊急事態宣言関係で、公開を制限されてしまい、限定した形での一般公開となってしまいましたが、その様子を映像にまとめたものが公開されておりますのでご覧ください。
記念出版:内田あぐり監修『膠を旅する』(青木茂・上田邦介・金子朋樹、他著
2012/5 国書刊行会)B5変形・240頁・本体3,800円
YouTube 「膠を旅する 表現をつなぐ文化の源流」
https://www.youtube.com/watch?v=128vWyMogb0
2021年7月12日 |
トピック:和紙情報
« 古い記事
新しい記事 »