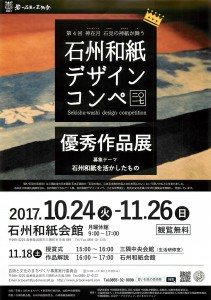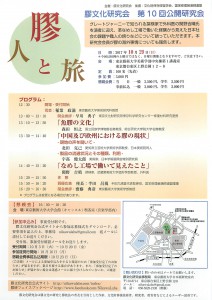和紙情報
◆和紙情報
展覧会
かな料紙 ー小室かな料紙工房展示会ー
会 場:GALLERY 心 〒110‐0015 東京都台東区東上野18-14
TEL 03(3845)5010
会 期:2018年1月19(金) ~ 1 月28日(日) 11 : 00 ~18 : 00
(月曜休館、祝日の場合開館・翌平日休館)
入 場:無料
ワークショップ:
期 間:1月20日(土)~28日(日)
時 間:午前11時~12時 (約60分を予定)
定 員:1日6名様 (要予約)
費 用:お1人様3,500円
予約受付:12月25日(月)から 工房にて受付ます。
電話0294-82-2451(午前9時~午後18時)
体験内容:基本的な砂子の撒き方を体験。使用する料紙は179×282mmを5枚(A4より少し小さいくらいです)予定。
実 演:期間中随時行ないます。(ワークショップ中はお休みです)
2012年11月に昭和女子大で開催しました第20回和紙文化研究会「和紙に美と技を求めて―加飾紙の世界―」(和紙研主催)の講師としてお願いいたしました小室 久さん、講演に加えて貴重な加飾技術と工程の実演ライブ中継をして、観客に好評をいただきました。(下記写真参照)また、和紙研の研修旅行でも常陸太田市の工房までお邪魔しました。今回は様々な装飾料紙と出会い、その実演を間近でみれる貴重な機会です。
ギャラリーHP:http://www.galleryshin.tokyo/2017/12/13/post-5156/
工房HP:https://kanaryoshi.com/2019/
Email:info@galleryshin.tokyo
第20回和紙文化講演会小室講師実演ライブ風景
2018年1月8日 |
トピック:和紙情報
◆和紙情報
展覧会 東京国立博物館
『2017年ユネスコ「世界の記憶」登録記念 朝鮮国書―朝鮮通信使の記録』
会 期:2017年12月5日(火)~12月25日(月)
時 間:9:30~17:00(入館16:30まで)
休館日は月曜日(月曜日が祝日または休日の場合は開館し、翌平日が休館)
会 場:東京国立博物館 日本美術(本館)
〒110-8712 東京都台東区上野公園13-9
料 金:一般620円、大学生410円
本年1月に招聘講師の高橋裕次先生に「朝鮮国書の料紙」として発表していただきました。東京国立博物館や宮内庁書陵部、京都大学総合博物館等に所蔵されている朝鮮国書について、繊維分析等の詳細な調査が行わていることを紹介していただきました。
展示
龍文朱塗箱 朝鮮時代・17~18世紀〔重文〕
朝鮮国王国書別幅 朝鮮国王李琿・光海君 朝鮮 朝鮮時代(1617)〔重文〕
朝鮮国書(部分)朝鮮国王李淏・孝宗 朝鮮 朝鮮時代・乙未年(1655) 〔重文〕
詳細につきましては以下HPにてご確認ください。
http://www.tnm.jp/modules/rblog/index.php/1/2017/12/07/
http://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1894
2017年12月19日 |
トピック:和紙情報
◆和紙情報
特集“神々しい色艶と音色、温かくそして凛とした和紙、雁皮そして越前鳥の子紙” 【1】
― 越前鳥の子紙が国の重要無形文化財に指定、越前生漉鳥の子紙保存会が保持者の認定を受けて ―
本年8月に重要無形文化財の指定及び保持者の認定等について文部科学大臣に答申されたことをお知らせいたしましたが、10月2日に指定(下記参照)、23日に認証式が行なわれました。和紙では過去同指定に「石州半紙」・「本美濃紙」が1969年、「細川紙」が1978年に受けていますが、素材の違い、そして和紙を取り巻く状況が大きく変化していることなどから、このことは越前和紙のみならず、現在そして将来の和紙にとって重要なことと考えられます。
重要無形文化財 名称:越前鳥の子紙
保持団体 名称:代表者 越前生漉鳥の子紙保存会 会長 栁瀨 晴夫
事務所の所在地
福井県越前市 新在家町8-44 福井県和紙工業 協同組合内
今回は保持団体の柳瀬晴夫会長と越前の次世代を担う越前和紙青年部会の山下寛也会長に、指定を受けての思いをご執筆をいただきました。また、「鳥の子紙(とりのこし)」とは何か。福井県和紙工業協同組合のご協力を得て「鳥の子紙」の歴史、主原料、紙漉き工程を掲載誌し、和紙の王者と言われる雁皮(がんぴ)100%の「鳥の子紙」をご紹介します。
「越前鳥の子紙は何を奏でるか」
越前生漉鳥の子紙保存会会長 柳瀬晴夫
「越前鳥の子紙」は、原料に国産雁皮のみを使用して伝統的な製法と用具を使って漉かれた紙で、2017年(平成29年)10月2日に重要無形文化財の指定を受け、「越前生漉鳥の子紙保存会」が保持団体として認定されました。
「越前生漉鳥の子紙保存会」は2015年3月に発足しました。それ以降、原料である雁皮の採集に春の山中を探し回り、その後皮こき、煮熟、ちり取り、秋には種取り、そして紙漉きと一連の作業を会員で協力して行っています。
この保存会には、16の製紙事業所の29名が所属しており、20歳代から60歳代までと幅広い年齢層で構成されています。
所属する工場も異なり、年齢の幅もある職人たちが同じ工房内で紙漉きに関わる作業を行う事は、近年には無かったと思います。
この様な環境の中で作業を行いながら、会話の中から仕事上のひらめきが生まれて、産地内での創作意欲が生まれるきっかけとなれば良いと思います。
自然の恵み、歴史と伝統、人々の努力と知恵、これらを基に紙を漉き、伝えられてゆく「技」から生まれる「越前鳥の子紙」。この紙をより多くの人に使って頂き、また、この紙に工夫を加えて古に漉かれていた紙の復元や、新たなる和紙を創出して行く事を目指して、これからも紙漉きを楽しみながら継続して参ります。
「重要無形文化財指定と次に繋ぐもの」
越前和紙青年部会 会長 山下寛也
越前和紙青年部会は、技術継承と後継者育成を軸とし活動を行っています。この度、越前鳥の子紙が重要無形文化財に指定され研修が本格化するにあたり、これまで研修に青年部会として参加していた形から、当部会から代表して数名が越前生漉鳥の子紙保存会の研修生として学び始めることとなりました。
これまで、越前和紙は様々なニーズに応えるべく、楮はもちろんのことパルプや輸入原料も用い、時間や労力に無駄のないようと努めてきました。このような努力は越前和紙が産業として大きく育った一因なのかもしれません。そうした現状の中で、保存会の研修において原料の調達や作り方から紙漉きや紙干しという一連の技術を皆で学ぶ機会を得たことで、青年部会として伝えていくべきことは何であるかを改めて考えていかなければと感じています。
また、一方では和紙の需要の減少や工場数の減少という現実もあります。紙を漉くだけでなく紙をどうみせるか、どう発信してくのかが重要になってきた今、青年部会としては、創作和紙の製作や展示、ワークショップを通して越前和紙の技術や新たな魅力もより多くの方々に伝えていかなければと思っております。
越前和紙のより一層の発展に向けて越前生漉鳥の子紙保存会で多くを学び、伝統の技を絶やすことなく後世に伝えるべく、より厚みのある青年部会として一同邁進してまいります。
①原料の作り方を学ぶ当部会長
②紙漉きの指導を受ける当部会会員
「越前鳥の子の歴史と主原料」
「鳥の子」とは
古代の斐紙と同じく雁皮を原料とする紙で、嘉暦三年(1328)ころの記録とされる『雑事記』に鳥子色紙とあるのが、初見とされている。延文年間(1365?61)の『延文百首』にも「鳥子色紙」とあり、『後深心院関白記』の延文元年(1356)十二月二十五日の条には、「料紙鳥子・同紙二枚を以て之をつつむ」と記されていて、鎌倉末期から鳥の子の呼称が一般化したと考えられる。その紙名については、『下学集』に「紙色鳥の卵の如し、故に鳥子というなり」と説明しており、『撮壤集』は「卵紙」(とりのこ)と表記している。
平安時代は「薄様」に対して厚様の雁皮紙を「鳥子」とよんでいたとも考えられる。しかし、近世にはすべての雁皮紙を鳥の子とよぶようになった。
『延文百首』にみられるように詠進料紙であり、あるいは写経料紙となり、ときには公文書用紙ともなった。とくに滑らかで堅く、耐久性のある強く美しい紙であるため、上層階級では永久保存を期待する書冊に愛用された。
中世から近世にかけての主産地は、越前と摂津の名塩で、襖用の間似合鳥の子(間似合判の鳥の子。間似合は半間(三尺)の間尺に合う紙の意味。横幅は三尺一寸ないし三尺三寸。縦幅は一尺二寸ないし一尺三寸で、五枚で襖片面を貼ることが出来る。)
「越前鳥の子」主原料
「雁皮」〈がんぴ〉
ジンチョウゲ科の植物。
雁皮の字が初めてみえるのは「明月記」で寛喜二年(1230)三月に雁皮の花が開いたと記している。
雁皮は栽培がむずかしく、野生のものを採取している。高さ1?1.5㍍、葉は互生し、卵形で裏に絹糸状の毛をもち、夏に枝の頂にジンチョウゲに似た淡黄色の小花を咲かせる。
靭皮繊維の長さは平均3.16㍉で、その質は優美で光沢があり、平滑にして半透明、しかも粘着性に富んでいるので、こしの強い緻密な質の紙となる。「越前紙漉図説」(小林忠蔵)によれば敦賀の菅浜産を上等品としている
その他の原料
「楮」〈こうぞ〉
クワ科カジノキ属の落葉低木。
和紙の主原料でヒメコウゾ、カジノキ、ツルコウゾがある。カジノキは雌雄異種、ヒメコウゾは雌雄同種で、厳密にいえば異種の植物であるが、容易に識別できないので、紙漉きたちは同種のものとして扱い古代には穀あるいは紙麻(かみそ)、近世には楮(こうぞ)と記している。
楮の靭皮繊維は麻についで長く、麻の平均14.4㍉に対して楮は平均9.73㍉で幅は平均0.02㍉である。そして繊維の絡み合う性質が強いのでその紙は粘り強く、耐久力のある強靱な紙となり、和紙のもっとも主要な原料である。
「三椏」〈みつまた〉
ジンチョウゲ科の落葉低木で、枝が三つずつに分枝するのが特徴。
伊豆の三須家文書によると、慶長三年(1598)三月四日付徳川家康黒印状は、修善寺の紙工文左衛門の雁皮、三椏の伐採権の独占を認めており、近世初期に三椏は和紙原料として導入された。明治期からは大蔵省印刷局製造の紙幣用に用いられた。
三椏の靭皮繊維の長さは平均3.6㍉、幅は平均0.02㍉で光沢があり明治期には輸出用コッピー紙の原料で雁皮に代用され、鳥の子でも雁皮に代わる主原料となっている。
「鳥の子 紙漉工程の詳細」
来月号では福井県和紙工業協同組合の石川浩理事長に「越前生漉鳥の子紙保存会とこれから」と全国手すき和紙連合会の五十嵐康三会長より「日本の手漉き和紙の中の雁皮紙」の掲載を予定しております。
2017年12月12日 |
トピック:和紙情報
◆和紙情報
碧い石見の芸術祭「第4 回 石州和紙デザインコンペ 優秀作品」
テーマ:石州和紙を活かしたもの
会場:石州和紙会館 〒699‐3225島根県浜田市三隅町古市場589
TEL 0855-32 -0098
会期:2017年10月24(火) ~ 11 月26日(日) 9:00 ~17: 00
(月曜休館、祝日の場合開館・翌平日休館)
主催:芸術と文化のまちづくり事業実行委員会
開催概要:
日本を代表する伝統文化「石州半紙の技」を生かした石州和紙を素材として、現代を生きる私たちに生活にうるおいや、楽しみ、くつろぎを与える様々なデザインの提案。
募集内容:
募集コンセプト:『石州和紙を活かしたもの』
出品規定:石州和紙を主な素材として使用した作品
サイズ:1m x 1m x 1m 以内
関連HP
https://www.artaoiiwami.com/デザイン2017/
「碧い石見の芸術祭」は日本画家である石本正画伯(1920~2015)の「石見の地に、心ある本物の作品と文化を残したい」という思いをもとに生まれたもので、石本正日本画大賞展を柱にいくつか地元の文化を織り交ぜた展覧会を開催し発信しています。このコンペもその一つです。
関連HP:https://www.artaoiiwami.com/
チラシ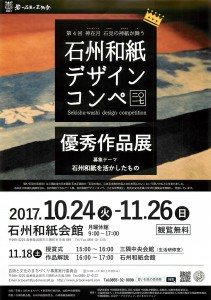
2017年11月8日 |
トピック:和紙情報
◆和紙情報
研究会・講演会
膠文化研究会第10回公開研究会「膠 人と旅」
関連Web
膠文化研究会公式サイト http://nikawalabs.com/index/
膠研フェイスブックページ http://www.facebook.com/NikawaLabs
日 時:2017年10月29日(日)
会 場:東京藝術大学美術学部中央棟第1講義室
東京都台東区上野公園12-8
定 員:100名(先着)
参加費:3,000円
懇親会費:当日支払:一般 3,500円、学生 2,500円
事前払込:一般 3,000円、学生 2,000円
主 催:膠文化研究会
後 援:文化財保存修復学会、国宝修理装潢師連盟
<プログラム>
12:30 開場・受付開始
司会:稲葉政満 東京藝術大学美術研究科教授
13:00-13:10 開会挨拶:早川典子
東京文化財研究所保存科学研究センター修復材料研究室長
13:10-13:50 「魚膠の文化」森田恒之
国立民族学博物館名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授
13:50-14:40 「中国及び欧州における膠の現状」
-現地の声を聞いて- 北田克己
愛知県立芸術大学美術学部教授、日本美術院同人
-製品の流通状況とその種類、利用- 宇髙健太郎
美術家、日本学術振興会特別研究員
14:40-15:20 「なめし工場で働いて見えたこと」関野吉晴
探検家、武蔵野美術大学造形学部教授、外科医
15:20-15:50 休憩
15:50-16:20 質疑応答 座長:半田昌規
半田九清堂代表取締役、国宝修理装?師連盟理事
16:20-16:30 閉会挨拶:斉藤典彦 東京藝術大学美術学部教授
懇親会
16:50-18:20
会 場:東京藝術大学大学会館(キャッスル)喫茶室(音楽学部内)
*プログラムは変更になる場合があります。
<参加申込み>
事前受付制です。
参加応募様式をダウンロード、必要事項を記入の上、件名に「第10回公開研究会」と
明記して、膠研事務局 nikawalabs@gmail.com 宛メールに添付してください。
受付後、参加受付確認メールをお送りします。
受付期間:10月3日(火)~10月20日(金)
参加費・懇親会費払込期限:10月23日(月)
参加証発行開始:10月16日(月)
<ご注意>メールによる参加申込みをすると、確認のため「参加受付完了のお知らせ」が届きますが、数日を要する場合があります。
<申込み、問い合わせ先> 問い合わせはメールでお願いします。
膠文化研究会事務局 メール: nikawalabs@gmail.com
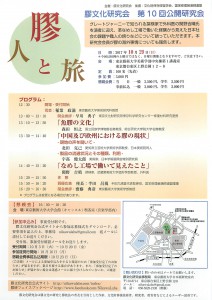
2017年10月10日 |
トピック:和紙情報
« 古い記事
新しい記事 »