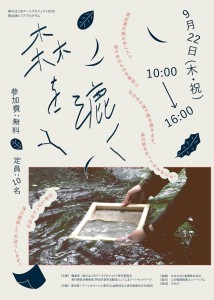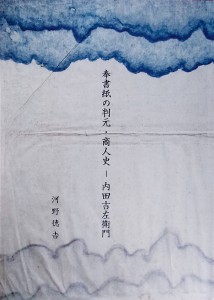和紙情報
◆和紙情報
特別展 「丹後の紙漉き -和紙と生きる人びとのあゆみとゆくえ-」と図録紹介
会 期:平成28年10月15日(土)~12月11日(日)
会 場:京都府立丹後郷土資料館
〒629-2234 京都府宮津市字国分小字天王山611-1 TEL 0772-27-0230
主な展示品:
畑製紙農業協同組合資料(宮津市 近代 畑自治会蔵)
丹後・丹波の手漉き和紙生産用具(宮津市・京丹後市ほか 近代 当館蔵)
手漉き和紙製品(綾部市・福知山市ほか 近代~現代 当館蔵)
紙布(福知山市 昭和時代 個人蔵)
紙衣(福知山市 昭和時代 福知山市蔵)
映像「京の和紙」(京都府 1975年)
「黒谷和紙」(黒谷和紙協同組合 2016年)
※会期中に展示替えをおこないます
関連事業:
文化財講座 「紙すきの歴史と技術」
日 時:11月12日(土) 13時30分~ 会 場:第一研修室
講師:京都府立山城郷土資料館 資料課長 横出洋二
図録の紹介 和紙研有志“一押し”書籍
『丹後の紙漉き -和紙と生きる人びとのあゆみとゆくえ-』
発 行;京都府立山城郷土資料館
発行日:平成28年10月15日
編 集:京都府立山城郷土資料館
判 型:A4判 96頁
装 丁:並製 オールカラー
価 格:600円
京都府立丹後郷土資料館
http://www.kyoto-be.ne.jp/tango-m/cms/index.php?page_id=0
2016年12月8日 |
トピック:和紙情報
◆和紙情報
緊急報告及び急募「トロロアオイ希望者求む」
2004年1月 に設立された「小川町トロロアオイ生産組合」は、休講・不耕作地を解消するとともに、途絶えていた製紙材料の自給を目指しており、2001年から試験生産をはじめ、生産・需要の安定を目指して取り組んでいます。
ところが、今年は大量注文が見合わせとなってしまい、1000kgほどの余剰在庫となるようです。近年生産が安定してきた最中にあって、この事態に生産者の方々が困っているようです。
そこで、急ではありますが、全国の製紙関係の方々にご利用いただくことはできないかということで、緊急公募することになったということです。時間的に厳しいところですが、ご利用希望の方は下記お問合せ・ご注文下さい。

お問合せ・申込み先
JA八和田支店 経済センター 担当:田幡(タバタ)さん
〒355-0312 埼玉県比企郡小川町上横田556
電話0493-72-5275 FAX 9493-74―0857
申込み期間:10月末まで
価格:10kg 2500円(税込) ご注文は10kg単位でお願いします。
送料:宅急便の着払いで発送。 請求書を同封しJAの指定口座へ振込。
2016年10月20日 |
トピック:和紙情報
◆会員情報
展覧会
ESTUARY ARTS CENTERE「Fukuoka Day・福岡デイ ギャラリー展 」
青木真奈美 会員関係
会 期:2016年9月24日(土)~25日(日)10:00~16:00
会 場:PO Box 480 214B Hibiscus Coast Highway,Orewa New Zealand
電 話:09 4265570
http://www.estuaryarts.org/
お問い合わせ先:aklart2016@gmail.com
※Orewaというビーチのあるリゾート地のギャラリーです
9/3(土)にニュージーランドで開催した、福岡市とオークランド市の姉妹都市提携30周年を記念したイベントFukuoka Dayに参加した日本人アーティスト作品のギャラリー展示です。
今回、和紙造形作家 青木会員が、流し漉きの手法で作成した造形作品(和紙)で参加します。
・何点かの作品の販売も行います。

2016年9月7日 |
トピック:和紙情報
◆和紙情報
「森を漉く」ワークショップ
日 程:2016年9月22日 (木・祝) 10時?16時
集 合:西会津国際芸術村
会 場: 西会津町奥川地区 寺清水広場(塩集落周辺)
参加費:無料
定 員: 10名
お問い合わせ: 0241-47-3200 西会津国際芸術村 担当:楢崎
morinohakobune.nishiaizu@gmail.com
www.morinohakobune.jp/
※ ぬれても良い服でお越しください!
☆スケジュール
10:00 西会津国際芸術村集合、広場に移動
10:15~ 体験説明、加工方法の実演説明動
10:45~ 森の中を散策、材料探し
11:20~ 材料加工
12:00~ 昼食休憩(各自でご用意ください)
13:00~ 紙漉き開始
14:30~ 休憩、圧搾
15:00~ 紙干し
16:00~ 現地または芸術村で解散
<主催>
福島県|森のはこ舟アートプロジェクト実行委員会
実行委員会事務局:NPOふくしまアートネットワーク
<共催>東京都/アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団) <協賛>日本たばこ産業株式会社 <協力>心の復興推進コンソーシアム
<助成>文化庁
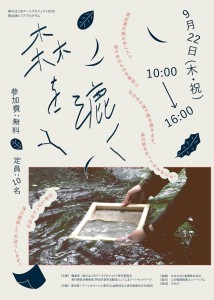
2016年9月7日 |
トピック:和紙情報
◆和紙情報
新刊紹介『奉書紙の判元・商人史―内田吉左衛門』
部 数:限定300 部
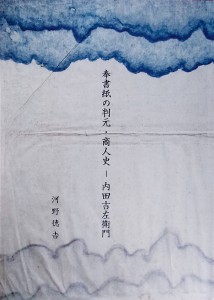
著 者:河野徳吉
編 集:越前和紙を愛する会
発 行:紙の文化博物館
装 丁:A4 判・並製・70 頁
発行日:2016 年4月発行
価 格:1,500 円(税込)
中世の紙の主要な消費層は公家・僧侶と武家でしたが、近世には町人層が加わり、紙の需要は著しく増大し、重要な商品となります。
越前五箇では、三田村家・河内家など御紙屋として格式の高い奉書・鳥の子の
「御用紙」が主流だったのが、江戸中期元禄の頃になると、紙の流通が格段に拡大し、御用紙の「誂物」に並んで、一般の「商物」の紙の種類・量もいよいよ増加し、国内・他国販売仲買の勢力は強大な地歩を築きます。中でも有力だったのは内田吉左衛門、野辺小左衛門で、商業紙本的活動は酒造・布類取引等、諸方面にわたり、圧倒的な地位を占めていました。
本書は河野徳吉先生が集録された内田家文書、および三田村家・河野家文書などを検証し、三都(江戸・京都・大阪)を舞台に総合商社活動を展開し、福井城下の両替商・回船問屋と並ぶ豊かな財力で福井藩の懐を賄った奉書判元・仲買人の内田吉左衛門の栄枯盛衰を小冊子にまとめたものです。
(越前和紙を愛する会・紙の文化博物館の案内より)
ご購入について
ご遠方の方々には郵送にも対応しております。詳細は下記までお問合せ下さい。
紙の文化博物館(現在工事中につき、仮事務所はパピルス館2F)
〒915-0232 福井県越前市新在家町8-44 電話0778(42)0 016
2016年8月8日 |
トピック:和紙情報
« 古い記事
新しい記事 »